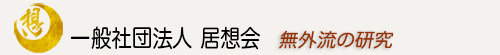無外流の研究
無外流刃引之形
刃引之形の動画
無外流は姫路藩において、剣聖・髙橋赳太郎によって幕末から明治にかけて受け継がれました。そして、昭和の時代に入ると、その子である秀三・赳行へと伝承され、現在に残る「刃引之形」が継承されました。これは無外流の形として現存する唯一のものです。
現代において「正統な無外流」といえるものは、この姫路藩と土佐藩に伝わるもののみとされています。居想会では、この「刃引之形」を基に、古流の動きを取り入れた居想会独自の表現を試みています。
無外流「刃引之形」の特徴として、相手の剣を受け流すのではなく、受け止める動きが多く含まれます。そのため、真剣で稽古を行うと、刀の刃が傷んでしまうことも避けられません。このような形について、居想会の動画を見た方の中には、「日本刀が傷むからあり得ない形だ」という意見もあるようです。
しかし、実戦を想定した場合、すべてを体捌きや受け流しだけでしのげると考えるのは、過信ではないでしょうか。相手の剣をしっかりと受け止める稽古もまた、重要であると考えます。
誤解を恐れずに言えば、刀は「使えば消耗する道具」です。そのため、大切な刀を守る最良の方法は「使わないこと」かもしれません。しかし、無外流という武術を学ぶ上で、刀をどのように扱うべきかを追求し、稽古を通じて実戦的な技術を磨くことこそが、私たちの目指す道です。
無外流・刃引之形の解説
無外流・刃引之形:一本目
打太刀の真向から振り下ろされる剣を、仕太刀は刃で受け止めます。このとき、両者は均衡が保たれた状態にあります。打太刀が剣を押し出せば、仕太刀はそれを流していくことができるため、打太刀も容易には動けない立場となります。
仕太刀は、相手の剣との圧を変えないよう注意しながら左半身を寄せて柄を取ります。この際、押したり引いたりすれば均衡が崩れるだけでなく、その力加減が相手に伝わり、逆に制されてしまいます。圧を変えずに動くためには、日頃の稽古で行う「半身の切り返し」の動きが非常に有効です。
左手で柄を取った後も、押したり引いたりせず、剣を直立させていきます。このとき、剣を立てる方向は「刀の交点」と「相手の鳩尾」を直線で結んだラインに沿う必要があります。このラインを外れることは許されません。また、剣を立てる際には、螺旋状に動かすのではなく、錐(きり)のように直線的に動かすことが重要です。
近年では、新たなバリエーションとして、「切り返して腰を打つ」という稽古も取り入れています。この動きは「半身の切り返し」を鍛えるための良い稽古方法となっています。
無外流・刃引之形:二本目・三本目
ハ相の構え(三本目は上段)から真向に斬り込みます。打太刀は、受けた剣の交点から右肩を抜いて体勢を変えようとするため、仕太刀はその動きに逆らわず、十分な間合いを取ります。
このとき、先走って勝手に左側(三本目では右側)へ受け流す動作をしてはいけません。打太刀が真向に斬り込む気配を十分に感じ取ってから、受け流しの体勢に移ることが重要です。もし先走ると、打太刀の剣が追ってくる危険があります。
受け流しの際は、廻剣の要領で両肘を伸ばしながら動きます。その際、小手や頭を斬られない位置に剣を捌くよう注意します。
無外流・刃引之形:四本目
仕太刀が下段より小手をとりにゆきますが、打太刀の一瞬早く仕太刀の頭を狙います。仕太刀はこれを受け止めますが、しっかりと打ち込まれた剣筋はあやふやな受けでは剣がはねとばされますので、体で三角を作り同様に刀でも三角を作り、肘と膝を柔らかく使い打太刀の剣を凌ぎます。
凌いだ後は一本目の要領で剣を立てて、不利な状況を打破します。
無外流・刃引之形:五本目
仕太刀は上段より真向に斬ります。最初のうちは真っ直ぐに斬れません(言うは易し行うは難し)。斜めから打ったり、真ん中に来ても左右にずれたりします。力むほどに利き手に頼ろうとしますので、稽古の量と質が大切です。まず真っ直ぐでない自分を自覚し力む事をやめることです。
実際に斬る位置は打太刀の頭上、そして受け止められるはその上にある打太刀の木刀なので、打った後どのようにするべきか迷うことがあるでしょうが。迷わず鳩尾あたりに斬り込んでください。意識が木刀の交点にあると剣が浮き上がり、打太刀に腹を斬られます。剣を受け止められてもしっかりと打太刀の中心を押さえてゆく気持ちが大切です。
打太刀
打太刀の仕事は、仕太刀の良い部分をいかに引き出してゆくかです。
仕太刀の送り出す剣をガッと受け止めるのではなく、キャッチボールの時のように球を吸収するように受け止め、余裕をもって柔らかく受けることが大切です。
そしてアドバイスは一言にとどめること。くどくどと長いアドバイスは不要です。