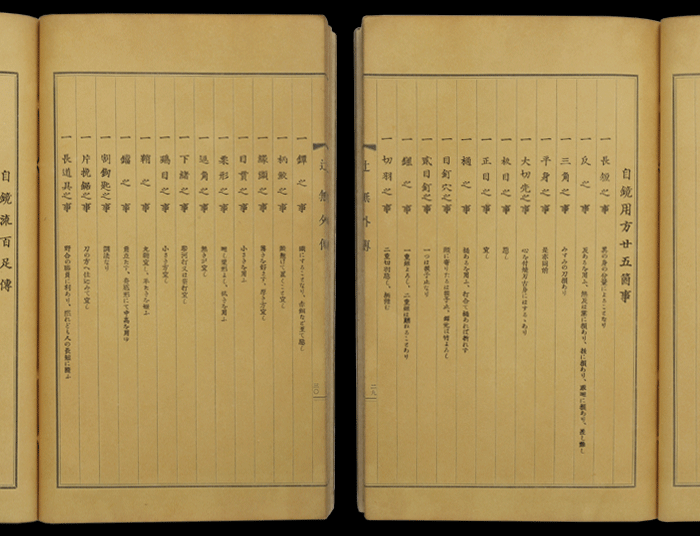無外流の研究
自鏡用方二五箇事
無外流居合の元となった自鏡流には刀剣について25箇の教えがあります。
江戸時代に書かれたもので現在では馴染みのない名称や用法もありますが、稽古の参考となる有意義な教えがあります。
参考文献:中川士龍著「無外真傅兵道考」
一、長短之事其の身の分量によることなり
源平時代から南北朝の頃までは、長大な刀が使用されたが、剣技の発達は長大な刀を必要としなくなった織田豊臣の時代には小銃が使用されるようになってからは甲冑も軽快となり、刀も長くて三尺前後になった。
徳川四代将軍家綱の治世、寛文十年に「帯刀寸尺の令」が発令されて「大刀は二尺八寸九分まで、脇差は一尺八寸を限りとす」と定められた。然しこれでも大刀は相当に長く、漸次短くなって、二尺三寸前後になった。技倆、力量、身体の大小により、己に適した刀を持つことがよいわけである。
二、反りの事反りあるがよろし、無反りは悪し
刀の反りは切断の必要上生じたものである。大体五分から七分位迄がよく、反りが深すぎると切断の時、刃筋が通り難い欠点がある。又反りの無い刀は切断よりも打撃になり易く、手元にひびいて斬り難いものである。適当な反りは抜刀や納刀にも有利である。
三、三角の事みすみの刀損あり
みすみという名称は、刀身のどの部分にも現在ない。鎬造りの刀の「三ツ角」は研磨の結果、鎬、小鎬と横手筋の合わさった部分である。刀剣鑑定家の権威である山田英氏に尋ねたが不明であった。三ツ棟即ち真の棟かとも考えてみたが使用上決して損とも思われない。
四、平身の事これ亦同様
脇差しなら兎も角、二尺以上の刀としては鎬のない平造りの刀身は、実践的な刀ではない。
五、大切先の事心は付焼刃、古身にするるものあり
大切先の刀は一見豪壮ではあるが、この刀には長巻を刀に造り換えたものがあって、実践的な刀とはいえない。「するるもの」とはすり減ったの意であり、肉がなくなっている刀身のことである。実用刀としては小切先または中切先を可とする。
六、板目の事悪し
板目肌の刀身は、折り返し鍛錬の度が少なく、大抵折り返し八回を限度とする。八回折り返すと重ねは二百五十六枚となる。私はかねて戦時中刀匠に十五回折り返しを命じて鍛錬させてみたが、研ぎ上げたところ無垢鍛えのようであった。十五回折り返すと重ねは三万二千七百六十八枚となる。板目では鍛錬が不足とみてよい。
七、正目の事よろし
正目即ち柾目のことであるが、柾目も十回か十二回折り返し迄の鍛錬位がよい所である。鍛錬のことを知らない人が何千回、何万回と鍛えるなど平気ではなしているが、そんなことをしたら、鉄は脆くなって役にたたなくなる。刀身は堅いと同時に粘りが必要なのである。故に柾目が肉眼で見える程度をよいとするわけである。
八、樋の事樋あるを用う、打ち合って折れず
刀身の棟と鎬の間に樋を掘ることは、刀身の目方を軽くすると同時にレールの原理と同じく、曲がり難く折れ難くなる。
九、目釘穴のこと頭に寄りたるはねじ止め、鍔元は竹よろし
中心(なかご)尻の目釘穴にはねじ止めの目釘を用い、関に近い中心穴の目釘は竹を使用するのがよい。実用的には、これに越したことはない。普通一般には関寄りの目釘、しかも竹のみが多く、茎尻(ながご)のねじ止めなど見かけないが刀剣を武器として戦うなら必要だと思う。
刀を振る時には、刀身は柄から抜け出すので、目釘で止めているが、この抜け出す力は振る刀に刀身の重量がプラスされるので、目釘がないと非常な速度で飛び出すのである。故に竹目釘だけなら、皮の厚い竹の丈夫な目釘を使用すべきである。私は何時も目釘の予備を持参することにしている。
割箸など目釘にしている人があるが、刀剣を使用する資格のない人である。最も注意すべきことである。
十、二つ目釘の事一つはねじ止めなり
前条参照
十一、ハバキの事一重ハバキよろし、二重ハバキは跳ねることあり
実践時代の太刀ハバキは凡て一重ハバキである。二重ハバキは世が泰平になってからのもので、実用的ではなく打ち合った時、外側の部分が跳ねて、刀身がガタガタになる怖れがある。
十二、切羽の事二重切羽悪し、柄ゆるむ
実戦用としては一重切羽即ち鍔の両側に一枚づつの切羽をはめるのがよい。飾り太刀とか儀杖用の太刀には三重切羽したものがあるが、これは装飾であって、実用刀としては不可である。
十三、鍔の事鉄にすることなり、赤銅など至って悪し
実用刀には鍛えた鉄鍔が最上である。彫刻などあまりない方がよい。赤銅鍔は重く、傷つきやすい欠点がある。赤銅鍔は古い時代には絶えてないもので、徳川の泰平の世になってからの産物で、鍔としての役目はなく、むしろ装飾である。
十四、柄鮫の事鮫かけて置くことよろし
柄木に鮫皮を貼りつけて、柄糸を巻けば柄糸もゆるまず、柄を握った時指のかかりもよく滑らないのが長所である。
十五、目貫の事小さきを用う
目貫の最初は、柄の表裏に短冊形の金属をくい違いに添えて柄糸を巻き、柄の補強に使用したものであるが、後には装飾の具なって、大形のものが現れるようになった。
大形の目貫をとりつけた柄は、握り締めにくい欠点があるので、小さい方が可とされたのである。
十六、栗形の事廻し栗形よし、低きを用う
刳(く)り形だという説もある。又栗の形をしているから栗形という説もある。栗形は鞘の外側にとりつけ、下緒を通す具であって、水牛、金属、木製がある。
廻し栗形とは、鵐目(しとどめ)をはめる所も丸くなっていて、鵐目を用いない。下緒の抜き差しに便利である。実用を主としたものであるがあまり見かけない。
高い栗形は抜刀、納刀の時に手ざわりになってよくない欠点がある。
十七、返角の事無きがよし
一般にさぐりという、逆角(さかづの)又は返角(かえりづの)ともいう。前方に鞘が抜けないための具であるが、脇差などよいが大刀には、前後の当て身などの場合、操刀上不便である。
十八、縁頭の事薄きを好まず、厚き方よろし
頭金は武用刀には金属製の厚手の方が当て身に有効である。又縁金は切断の際に刀の力が懸かる部分であるから、やはり厚手で丈夫なのがよい。実戦の場合で最も痛み易い部分は柄であるから、柄木の選定、縁金、頭金、柄糸の巻き方は最も大切なことである。
十九、下緒の事駿河打又は袋打よろし
下緒はタスキにするとか、敵を生け捕りにした時にくくるとか、抜き合った時に腰からはずれないように帯にくくりつけるとか、使用の目的は種々あったらしい。徳川中期以後に於ては、刀の外装のアクセサリーになったようである。窪田清音が天保十年に著わした剣法畧記の下緒の項を見ても、下緒の目的は記されていない。
「下緒は柔らかなのを用ゆるがよく、固い下緒はしまりがたくて解けやすいのでよくない」と窪田清音は冒頭に記している。駿河打ちとは、糸をあぢろに編んだもの。袋打ちとは、細い袋状に編んだ下緒のことである。いずれも柔らかである。長さは一尋(約六尺)が普通で、鞘の長さに応じて定めることも剣法畧記に記されている。
二十、鵐目の事小さき方よろし
鵐目(しとどめ)は柄頭の金具の両側にある柄糸を通す穴と、栗形の下緒を通す穴の両側にはめ込んだ小さな金具のことである。殿中差など装飾を主とした刀にはやや大き目の金無垢で造ったものもあるが、実用刀には小形のものが多い。糸のしまりも小さいほうがよろしい。
二一、鞘の事丸鞘よろし、平たきを嫌う
抜刀、納刀の際に固く締めた角帯の間で鞘を廻すので、丸みを帯びた鞘の方が操作がし易いためである。薄手の平たい鞘は廻し難いためである。
二二、鐺の事角経たず船底形にて中高を用う
鐺(こじり)は鞘の末端にとりつけた金具で、どろずりとも云う。鞘を腰に差す時、丸みのある中高の鐺が差し易くもあり、後方の敵に対する当て身には有効である。
二三、割鈎匙の事調法なり
わりこうがいと読む。こうがいの目的は、戦場で頭髪の手入れに用ゆるものである。割りこうがいは、こうがいを縦に二つにしたもので、合わせるとこうがいになり、二つに割れば箸の代用ともなる。古い時代には鉄製であるが後世になると、赤銅に定紋の象眼をしたりして一種のアクセサリーになった。
二四、片引鋸の事刀の方へ仕込みてよろし
実戦用には便利であったようである。私は未だ見たことがない。
二五、長道具の事野戦の勝負に利あり、然れども人の長短に随う
長刀ではなく、長道具であるから日本刀以外の長い武器即ち槍、薙刀、長巻などと思われる。野合即ち平野のような広い所では有利であろうが、使用する人の力量によって使用するのが適当で、誰でもというわけではない。