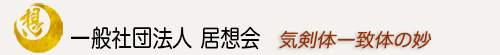気剣体一致の妙
居想無外流居合:神妙剣
神妙剣(旧・廻り懸り)について
居想会では、2009年9月より、従来の居合形「廻り懸り(まわりがかり)」を「神妙剣(しんみょうけん)」と改称いたしました。
本形は、不意に左側に出現した敵に対する対応を理合としたものです。古武道においては、「まず斬る」ことよりも、「敵を制し、中心を取る」ことが何より重要とされます。
主題と意義
敵が有利な位置にいる状況で、いかに素早く抜き付け、左方向へ転身できるか――これが「神妙剣」の主題です。その理合は、実戦的な古武道としての意味をより深めたものとなっています。
動きの工夫と緩みの理
重心を前に置いて走るような動きには、当然ながら慣性力が働きます。この力を無駄にせず、左方向へと転化するためには「緩み(ゆるみ)」が不可欠です。
力任せに回ろうとすれば、前進の勢いを止めるために踏ん張らざるを得ず、その結果、動きが一度止まり、時間的にもエネルギー的にもロスが生じます。
古武道としての居合を志すのであれば、この慣性の扱い方に対する工夫が必要となります。
形の展開
左の敵を感知した瞬間、両膝を抜いて重心と軸を左へ移しながら腹抜きを行います。左足の前を通る右足は、足を先行させず、体軸の移動に従って自然に捌きます。
抜刀した剣は、転身する右腰の動きに合わせて左側に向かい、敵の中心を正確に突いていきます。
その後、振りかぶる際には両肘を緩め、剣を立てて、二の太刀へとつなげます。